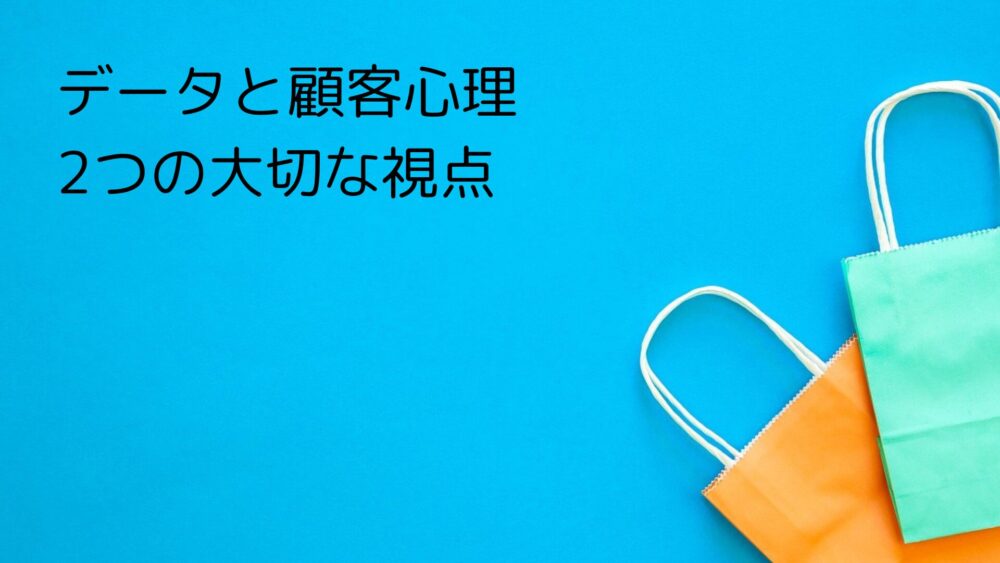市場ニーズと顧客心理を考慮しない事業は失敗する
起業して、
スモールビジネスを始めようと志し、
その時点での思いつきやアイディアのまま
事業化していくのはきわめて危険です。
継続的に利益が出る事業構築には、
市場ニーズや顧客の心理を
理解することが不可欠なのです。
「事業化したものの商品が全く売れない」
という失敗には枚挙にいとまがありません。
これを避けるためには、
事業構想段階での準備が
鍵となるなのです。
この記事では、
市場ニーズと
顧客心理を理解することが
なぜ重要なのか、
そして怠ることの危険性について
解説していきます。
データに基づく視点と顧客心理の視点から考える
事業構想段階で、
商品の市場を理解するために
大切な視点が2つあります。
それは、以下の2点です。
1️⃣ データに基づく視点
2️⃣ 顧客心理の視点
この2つの視点を理解して
事業に反映させることができると、
✅ 本当に参入価値のある市場かを見極められる
✅ お客さんの気持ちをつかみ、購入まで導ける
この記事では、
マーケティング初心者の方にも
理解しやすいように、
この2つの視点について
詳しく解説します。
1. データに基づく視点
事業構想段階で客観的なデータを重視する必要性
起業を志す人が
事業構想段階で市場を理解する際、
客観的なデータを重視することが
極めて重要です。
なぜなら、
市場の実態や顧客ニーズを正しく理解し、
仮説の精度を高めることが、
事業の成功確率を大きく左右するからです。
以下の4つの視点から、
その重要性を詳しく解説します。
1. 「市場性」と「競争環境」を把握|成長の可能性を見極める
(1) 市場規模の測定
事業の成否は、
市場の大きさや成長性に
大きく依存します。
市場規模が十分に大きく、
成長している分野であれば、
参入の価値が高まります。
例えば、
「日本のサブスクリプション型
家事代行市場は年間〇〇億円規模で、
年率〇%成長している」
といったデータがあると、
事業の可能性を定量的に評価できます。
市場規模が小さい場合
この様な市場では、
需要が限られ、
利益を上げるのが
難しくなります。
また、競争が激しくなった際に
事業の耐久力が低くなりがちです。
市場規模が大きく、成長中の場合
この様な市場では、
新規参入でも
収益化しやすくなります。
また、事業規模によりますが、
投資家からの資金調達がしやすい
という側面もあります。
(2) 競争環境の分析
競合に勝てるかどうかを見極めるために、
既存の競合企業がどのような
強み・弱みを持っているのかを
分析することが重要です。
✅ 競合の提供する商品・サービスの価格帯、品質、顧客層を分析
✅ 競合がどのようなマーケティング戦略を取っているのか調査
✅ 競争が激しい市場か、ニッチな市場かを判断
例えば、狙う市場が競争が激しい
所謂「レッドオーシャン」で
あることが分かったとします。
撤退の判断もあり得ますが、
どうしても参入したいのであれば、
独自性の高いビジネスモデルや
尖った顧客ターゲティングなど、
明確な戦略が必要になります。
デモグラフィックデータの活用
デモグラフィックデータ(人口統計データ)は、
「どんな人が、どんなニーズを持っているか」
を客観的に把握するのに役立ちます。
例えば、以下のような考え方ができます。
活用例:
店舗ビジネスの立地戦略
✅ 例:「地域の年齢層から見るカフェ・レストラン」
若者が多いエリア
→ トレンド性の高いカフェ
ファミリー層が多いエリア
→ 子供向けメニューやキッズスペースがある店
シニア層が多いエリア
→ 健康志向のメニューを展開商品・サービスのカスタマイズ
✅ 例:「地域の世帯人数から見る食事宅配ビジネス」
独身者が多いエリア
→ 一人分の時短料理・冷凍食品
ファミリー層が多いエリア
→ 大容量の食材セット・家族向け宅配サービス
3. 収益性と価格戦略を客観的に評価する
(1) 適正価格の設定
客観的なデータがなければ、
商品・サービスの価格設定を
適切に行うことができません。
市場調査を通じて、
以下の情報を得ることで、
価格戦略を最適化できます。
競合の価格帯
→ 安価/高価/プレミアム価格
消費者の価格許容度
→ 幾らまで払えるか
コスト構造と利益率
→ 価格設定の基準
例えば、
競合の平均価格が5,000円のところ、
自社のサービスを7,000円で提供するなら、
顧客が納得できる2,000円分の付加価値が
提供できているかの判断が必要になります。
(2) 課金モデルの検証
市場調査を通じて、
「どの課金モデルが最も利益を生みやすいか」
をデータで検証することができます。
サブスクリプション型(定額制)
従量課金型(使った分だけ課金)
フリーミアム型(無料+有料オプション)
例えば、
市場データを見ると、同業他社の70%が
サブスクリプション型で収益を上げている
と分かれば、検討してみる価値があります。
4. マーケティング戦略の精度を高め、失敗リスクを減らす
(1) 集客チャネルの最適化
データに基づいて、
どの集客手段が最も効果的かを
判断することができます。
SNS広告(Instagram・Twitter・Facebook)
検索広告(Google広告・SEO対策)
オフライン施策(チラシ・イベント・口コミ)
例えば、
「ターゲット層の80%がInstagramを利用している」
というデータがあれば、Instagram広告を優先する
のが合理的です。
(2) 初期投資と収益回収のシミュレーション
客観的な市場データをもとに、
どの程度の投資が必要で、
何ヶ月で黒字化するのかを試算できます。
初期投資額
→ 商品開発費、広告費、人件費
損益分岐点
→ 何人の顧客を獲得すれば黒字化するか
ROI(投資回収率)
→ 広告費1万円に対して、いくらの売上が期待できるか
まとめ
事業構想段階において、
客観的なデータを重視することは
以下の理由で重要です。
✅ 市場の成長性・競争環境を把握し、成功の可能性を見極める
✅ ターゲット顧客を明確化し、最適なビジネスモデルを構築する
✅ 適正価格の設定や収益モデルをデータで検証する
✅ 効果的なマーケティング施策を選定し、投資対効果を最大化する
データを軽視して、
「なんとなくイケそう」
と思うだけで事業を始めると、
顧客ニーズとズレたサービスになり、
失敗のリスクが高まります。
だからこそ、
事業構想段階での
データに基づく市場の理解は、
成功の確率を高めるために
欠かせないプロセスなのです。
2. 顧客心理の視点:「顧客の購買プロセスと悩みを深く理解する」
起業を志す人が
事業構想段階で市場調査を行う際、
顧客心理の視点を取り入れること
は不可欠です。
なぜなら、単に市場の規模や
競合情報を把握するだけではなく、
顧客の購買行動や心理的なプロセスを
深く理解しなければ、
実際に売れる商品やサービスを
設計できないからです。
ここでは、以下の2つの視点から、
調査の必要性を詳しく解説します。
(1) 顧客の購買に至るまでのステップごとの心理の理解
(2) 顧客の「痛み」や「悩み」の深掘り
1. 顧客の購買に至るまでの心理プロセスを理解する
消費者は商品やサービスを
「ただの選択肢」として見るのではなく、
心理的なステップを経て購入を決定します。
このプロセスを理解せずに事業を始めると、
「良い商品を作ったのに売れない」
という事態に陥ることがよくあります。
購買意思決定プロセス
一般的に、
消費者は以下のステップを経て
購買に至ります。
この流れを深く理解し、
それぞれの段階で
適切なアプローチを行うことが
調査の目的です。
🌟ステップ別消費者の心理
事業構想段階での調査のポイント
(1) 認知(Awareness)
「この商品(ブランド)があることを知った」
どのような方法でターゲットに認知されるか
(SNS、広告、口コミなど)
(2) 興味(Interest)
「なんとなく良さそうだな」
競合と比較して、自社のサービスがどこで興味を持たれるか
(3) 検討(Consideration)
「本当に自分に必要?」
顧客の購買を妨げる要因(価格・信頼性・使い勝手)を調査
(4) 比較(Evaluation)
「他の選択肢とどっちがいい?」
競合調査を通じて、自社の差別化ポイントを明確にする
(5) 購買(Purchase)
「これを買おう!」
どの決済手段や購入方法が好まれるかを調査
(6) リピート・推奨(Post-purchase behavior)
「満足した!また買おう」「友達にも勧めよう」
何が満足度を高めるのか、リピートや口コミを生み出す要因を分析
事業構想段階で考えるべき顧客心理のポイント
1️⃣ 顧客が最初に商品を知るチャネルはどこか?(SNS?広告?口コミ?)
2️⃣ どんな情報があれば興味を持つのか?(価格?デザイン?口コミ?)
3️⃣ どんな不安が購入を妨げているのか?(価格?使い方?サポートの有無?)
4️⃣ 競合と比較したとき、顧客にとって何が決定打になるのか?
5️⃣ どこの売場で、どんな決済手段で購入するのが顧客にとって便利なのか?
6️⃣ 購入後、顧客が満足し、リピートや口コミにつながる要因は何か?
このような視点で調査を行うことで、
顧客の行動を先回りし、
スムーズに購入へと導くことができます。
2. 顧客の「痛み」や「悩み」を深く理解する
市場には多くの
商品やサービスが存在しますが、
最も売れるのは
「顧客の痛みや悩みを解決する商品」
です。
そのため、
事業構想段階で市場調査を行い、
顧客がどのような悩みを抱えているのかを
深く分析する必要があります。
「痛み(Pain)」と「悩み(Desire)」の違い
痛み(Pain) = 「今すぐ解決したい、苦しい問題」
例)「腰痛がひどくて、日常生活に支障が出ている」
→ 解決策として、整体サービスや腰痛用のサポーターが売れる
悩み(Desire) = 「解決したいが、急を要しない願望」
例)「おしゃれな部屋に住みたいけど、手間がかかる」
→ 解決策として、簡単に模様替えできる家具やインテリアが売れる
事業構想段階で行うべき調査のポイント
1. 顧客の「本当の悩み」は何か?
表面的なニーズ:
「もっと効率的に運動したい」
本質的な悩み:
「時間がなくて続けられない」
「結果が出ないとモチベーションが下がる」
2. 顧客が最も辛いと感じている瞬間は?
「仕事で疲れた後にジムに行くのが億劫」
「朝起きると腰が痛い」
3. 顧客が求める理想の未来は?
「短時間で効果が出る運動方法」
「自宅でできる腰痛対策」
4. 顧客は今どんな解決策を使っているか?
既存の解決策の不満点を分析し、
より良いサービスを提供できるかを検討する
事例:ダイエット食品の調査
例えば、新しく
「満腹感を持続させるダイエットスナック」
を開発する場合、調査を通じて
以下のような顧客心理を把握できます。
顧客の悩み 従来の解決策 不満点 新商品で解決できること
| 顧客の悩み | 従来の解決策 | 不満点 | 新商品で 解決できること |
| 「食事制限がつらい」 | 低カロリー食品を食べる | 満腹感がない | 満腹感を持続させる |
| 「リバウンドが怖い」 | 置き換えダイエット | 長続きしない | 栄養バランスを考慮 |
| 「美味しくないと続かない」 | プロテインバー | 味が単調 | お菓子感覚で楽しめる |
このように、
顧客の痛みを理解し、
それを解決する提案で
商品やサービスを設計することで、
売れるビジネスを構築できます。
まとめ
✅ 購買プロセスの心理を理解し、顧客がどのステップで離脱するかを分析することが重要
✅ 顧客の「痛み」や「悩み」を深掘りし、それにフィットする商品・サービスを開発することが成功の鍵
✅ 調査を通じて、表面的なニーズではなく「本質的な問題」にアプローチすることが差別化につながる
成功するビジネスは
「商品を売る」のではなく、
「顧客の問題を解決する」
ことで生まれます。
そのために、
事業構想段階で調査を行い、
心理学的な観点から
顧客の本当の悩みを理解することが
不可欠なのです。
🌟AIを活用する市場調査について
個人事業主が市場調査を進める場合、
AIを活用する方法がオススメです。
こちらの記事で方法を
詳しく解説していますので、
是非ご一読ください!